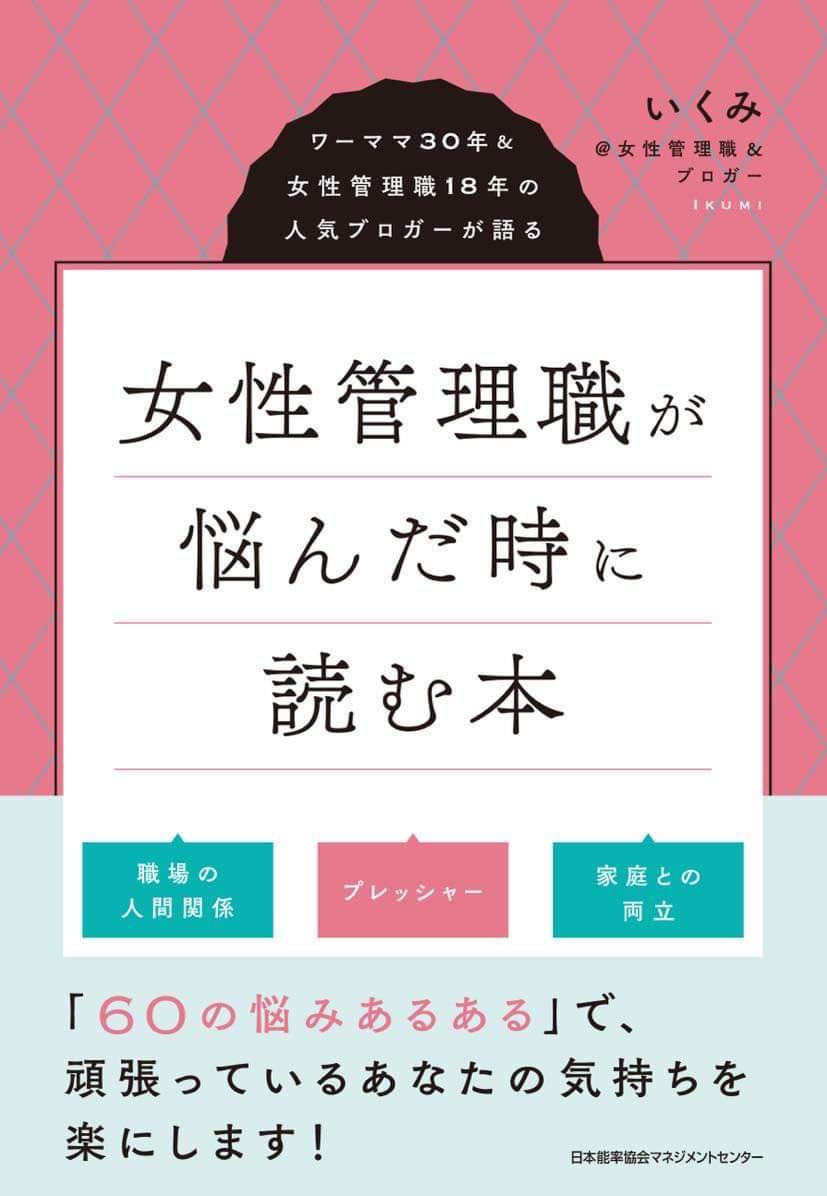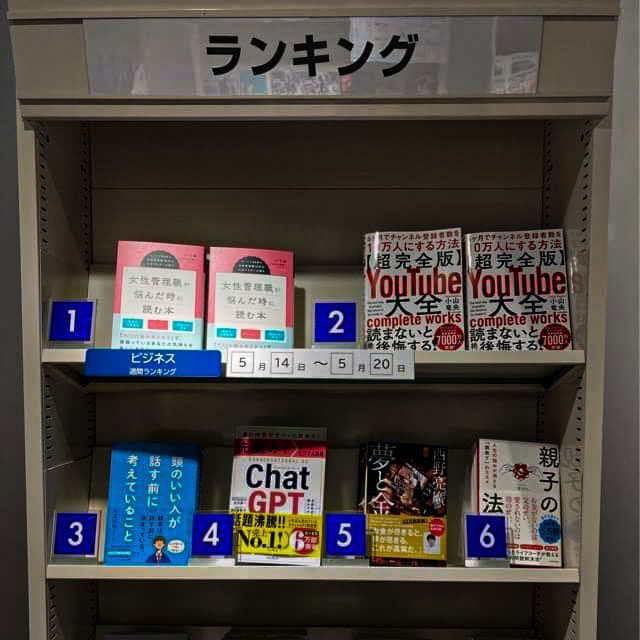こんにちは。女性管理職20年の いくみ(@nesan_blogger)です。
プライベートの場合ですと、今の世の中的にはLINEやメッセンジャーなどのチャットが主流となっていますが、会社だと、まだまだメールがそのメインでもあります。
直に話しをするとき(口頭)と違って、やはりメール文章というのはとかく誤解を生み出しやすい側面もあって、特に、言葉足らずに注意!
事例を交えて解説します。
「AさんとBさんが結婚されることとなりました」の落とし穴

まずは、笑い話から。
数年前の出来事なのですが、とってもインパクト大だったことです。
仕事の用件というよりは、ややプライベート寄りの用件でして、部下さんが結婚することになって、そのお祝い品についての案内でした。
幹事さんからのメール:AさんとBさんが結婚されることとなりました。つきましては、プレゼントを贈るのに有志のみなさまから◯◯円を出していただきたく…。
えーーっ??あのお二人お付き合いしていたんだ。知らなかった~~と、まずは衝撃。
とはいえ、おめでたいこと、喜んで協力しましょう。と幹事さんに◯◯円を渡しに行ったところ、
「ありがとうございます。それぞれのプレゼントに使わせてもらいますね。」
再び、えーーっ??それぞれって、どゆこと??
実は”落とし穴”だったんです。
「それぞれ」の一言が抜けていたこと
訝しげな私の様子を察してか、幹事さん。
「あ、AさんはAさんのお相手と、BさんはBさんのお相手と、それぞれご結婚されるのです」
これを聞いて、ズッコケそうになるわ、笑いが止まらなくなりそうになるわ…
いやいや、あのメールからはどうやってもそれ読み取れないから。例えば「AさんとBさんが『それぞれ』結婚されることになりました」のように「それぞれ」が入ってたら良かったんだけどねぇ~と伝えると、「確かにそうでした、すみません」と幹事さん。
なんとも微笑ましいものでもありましたが、肝心の業務直結の用件だと当然笑っている場合ではなく。
こうした、ちょっとした”言葉足らず”が影響して誤解に発展してしまうっての、結構ありがちなんですよね。

メール文章、言葉足らずへの防止法
口頭だとその場で確かめることもできますが、メールだと誤解が一人歩きしてしまう可能性大。
あれ?っと思っても「こういう理解で合っていますでしょうか?」といちいち返信しませんもの。
では、どういう点に気をつけたらいいかと申しますと、接続詞だったり修飾語だったりの抜けがないか?というチェックや、音読(オフィス内で声に出して読むのも難しいでしょうから、心の中で読む)をしてみるとか、場合によっては下書きを他の人に見てもらう、というのも一考です。
書いている本人はどうしても主観的になってしまいがちですから、より”客観を心がける”のが大切。
とにかく「言葉足らずへの防止法」書き言葉ですから、なおさら配慮することをお勧めします。

最後にひとこと
余談ですが、くだんの”AさんとBさん問題”。
偶然、Aさん(女性)のご結婚相手が、Bさん(男性)と同じ苗字だった、というオチがあって、この事案ユニーク過ぎました、笑。