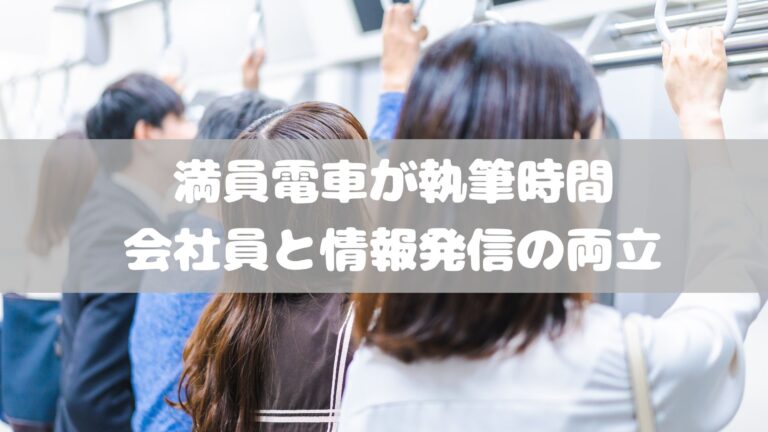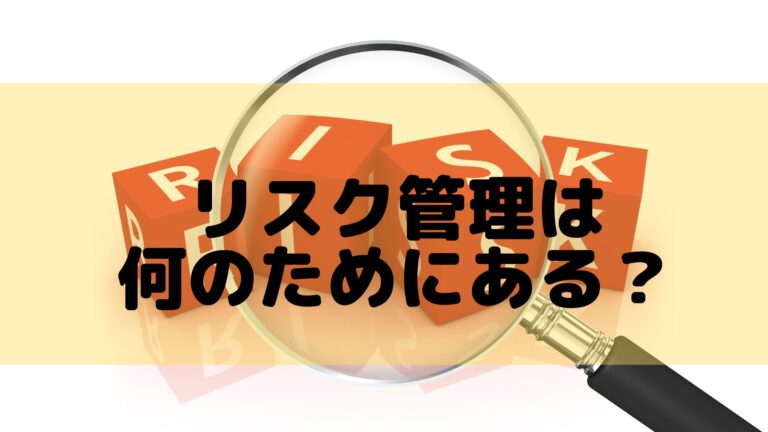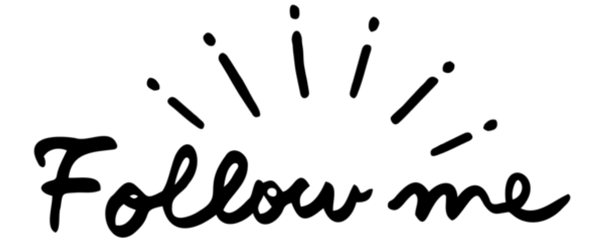【心理学】恩を感じない相手への対処法|恩送りの本質とは
こんにちは。女性管理職20年の いくみ(@nesan_blogger)です。
誰かのために一生懸命サポートしたのに、相手がそれを当たり前のように感じていた、特に恩義を感じていなさそうだ…そんな経験はありませんか?
「やるせない気持ち」になりますよね、私自身の経験を踏まえて解説します。
せっかくの支援が「通りすがりの一コマ」だったであろう出来事
誰かを支援するとき、私たちの心の中には「恩送り」の気持ちが芽生えます。
かつて誰かに助けられた経験があるからこそ、その温かい気持ちを次の人へ届けたい…純粋な想いがあるものです。
でも、時として現実は異なります。せっかくの支援が「通りすがりの一コマ」程度にしか受け止められないこともあるのです。
実はつい最近もそんな経験をしました。
ある事象について、たまたま私が先に経験していたため、後輩から相談を持ちかけられました。私自身もこのことについて、先輩からとても助けてもらったため、ぜひ、恩送りをしたいと考えて、時間を割いて彼女の相談に親身に答えたのです。
その後、無事にこの事象を果たされて、自分ごとのように嬉しくなりましたが、残念ながら以降にご本人からの連絡はありませんでした。
おそらく私のアドバイスは単なる「通り過ぎの一コマ」だったのでしょう。
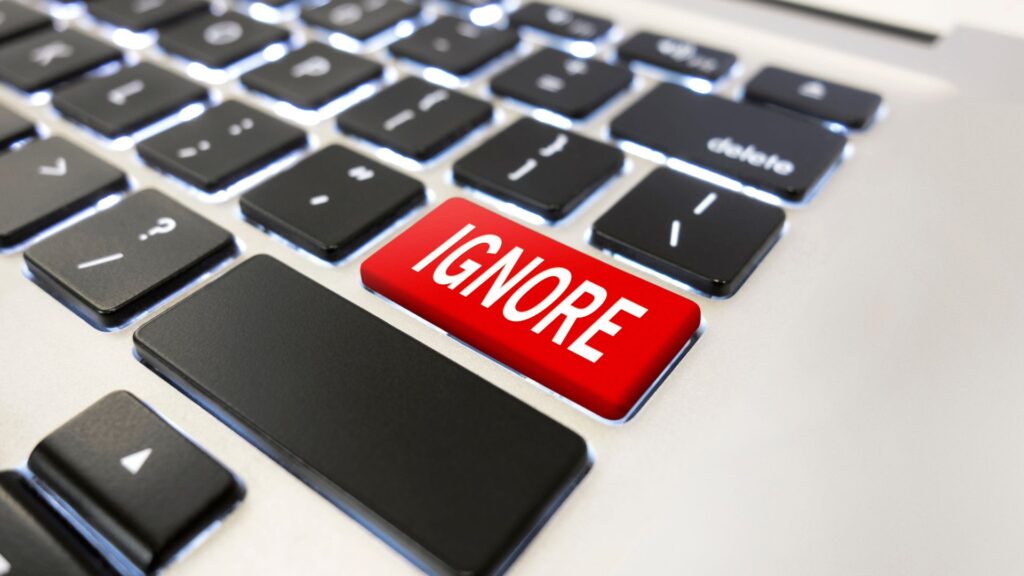
なぜ、このギャップが生まれるのか
このギャップが生まれる背景には、主に3つの要因があります。
まず、相手の置かれている状況です。素晴らしい実績をお持ちで、周りにも支援者が大勢いるような人にとって、私のサポートは「数あるサポートの中の1つ」に過ぎないのかもしれず。それはそれで仕方ないです。
次に、価値観の違いです。私は先輩から受けたご恩を次世代に送りたいと考えていますが、全ての人がそのように考えるわけではありません。恩を感じる感覚は、人それぞれなのです。
3つ目は、感謝の表現方法の違いです。直接的に感謝を伝え続ける人もいれば、心の中だけで留めておく人もいます。表現の仕方は十人十色。
こうしたギャップは自然なもの。これを理解することで、より自然な形で恩送りを続けていけるのではないでしょうか。
【具体的な解決策】恩送りを続けるための心構え

では、私は恩送りをしたくないのか?と言いますと、決してそうではありません。
心構えとして大切なことを書き出してみます。
まず支援する際の期待値を見直すことです。見返りを期待しないよう意識し、自分の行動そのものに満足感を見出していく。そうすることで、相手の反応に一喜一憂することが少なくなっていくのです。
次に大切なのが、「恩送り」の本質を改めて確認すること。誰かを助けることそのものに価値があり、その支援の連鎖は必ずしも直線的である必要はありません。私が支援した方は、また別の誰かの力になってくれるかもしれない。そう考えると、心が少し軽くなります。
そして、自分の気持ちに正直になることも欠かせません。相手が仮に塩対応だったとしても、やるせない気持ちを感じることは当然のこと。それを受け止めることも大切です。
そして、ある1人への支援をすることで、少々大袈裟かもしれずすみませんが、きっと社会全体への貢献にもつながっているに違いありません。
直接的な見返りがなくても、この視点を持つことで、より広い心で支援を続けていけるのではないでしょうか。
最後にひとこと
人への支援。それなりに自分も努力してのことですから、もちろん感謝してもらえるのは嬉しいですし、そうした言動に触れるととてもありがたい。
でもね。
例え反応がなかったとしても、これからも誰かの力になれることを喜べる自分でいたいです。
一部上場企業にて女性管理職21年の私が、あなたの悩み解決をお手伝いします。すでに女性管理職で活躍されている方、これから目指したいと思っている方、女性管理職とともにお仕事をされている男性の方、企業の育成担当者の方、どうぞお気軽にお問い合わせください。