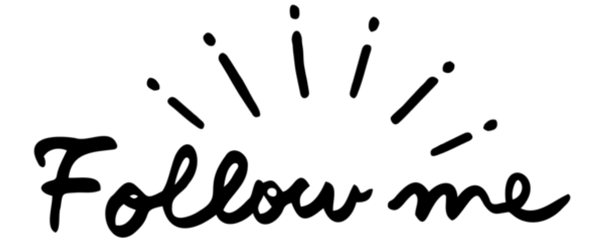【生成AI時代のブログ運営】依存と成長の狭間で悩むブロガーの本音
こんにちは。ブロガー8年目、これまで書いてきた記事が2,300記事超えとなった いくみ(@nesan_blogger)です。
この8年間、できる限り「毎日更新」を心がけてきて、その蓄積があったからこそ、拙著『女性管理職が悩んだ時に読む本』の初出版にも至れました。
ですから、これからもこのブログが私の発信のプラットホームであることは揺るぎありません。
とはいえ。
なかなか書けないこともままあって、そんな時には生成AIが強い味方になってくれます。
この記事では、生成AIをうまく活用しながら、なおかつオリジナリティを失わないブログ運営の方法について、私の葛藤や経験を踏ませて解説します。
ブロガーなら誰もが感じる?生成AI時代の葛藤
私はフルタイム会社員として働きながらブログ運営もしていますが、同じような状況にある人にはきっと以下の点には共感していただけることと思います。
仕事から帰って来て、疲れた頭で「今日は何を書こうか」とパソコンに向かう毎日。そんな中で、生成AIの存在は大きな救いとなる一方で、複雑な思いも募ります。
できる限り毎日更新していきたい…と目標に据えるものの、アイデアは徐々に枯渇してしまうのです。
「あれも書いた、これも書いた。次には何を書けばいいの?」ともすると、行き詰まってしまいそうになって、そこで、ぜひ生成AIの力を借りたくなる。
でも、それで良いのだろうか…。オリジナリティのある記事を書きたい気持ちと、限られた時間の中での葛藤は尽きません。

生成AIに頼るメリットと懸念点
生成AIの支援には計り知れないメリットがあります。
例えば、SEO対策されたキャッチーなタイトルの提案。これは、読者の皆様により多くの価値ある情報を届けるために欠かせない要素です。また、記事構成のアイデア出しや、モヤモヤとした思いの言語化のサポートも、大きな助けとなっています。
しかし同時に、似たような記事が出来上がってしまうこともありがちで、これが懸念点の一つでもある。
なぜならば”モヤモヤの正体”はある程度恒例化していたりするからです。
とはいえ、もはや生成AIに頼らず人力のみで物事をクリエイトしていく状況にはおそらく戻れなくって、これからもきっと頼っていきたい。
では、どう折り合いをつけていけば良いでしょうか?
解決への道筋:AI時代のブログ運営のあり方
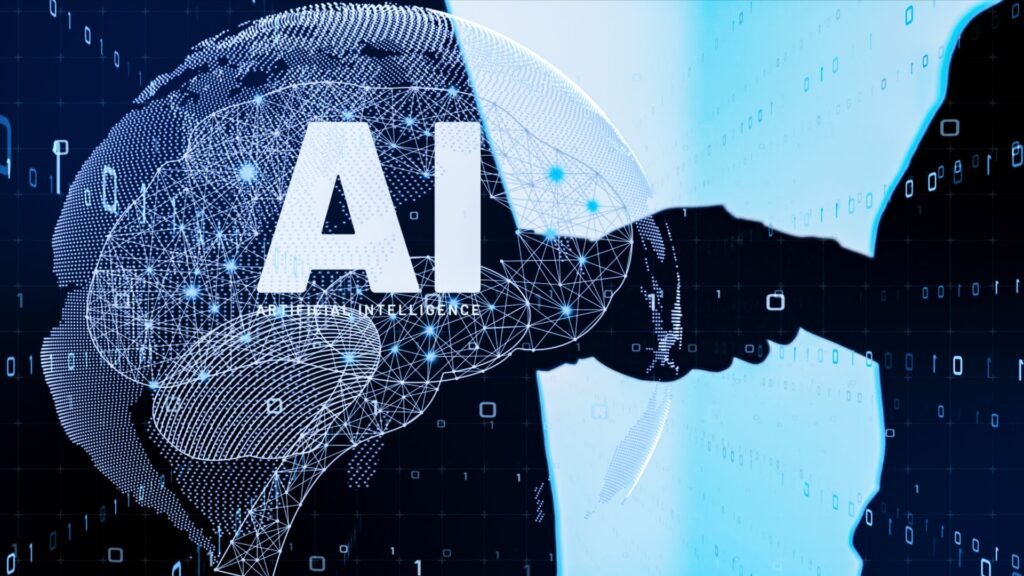
色々と試行錯誤を経て、私なりの答えにたどり着きました。
それは「AIを使いながら、自分らしさを失わない」という姿勢です。
具体的には、AIには「アイデアの種」を出してもらい、それを自分の経験や感性でアレンジしていく。最終的な言葉選びは必ず自分で行う。そうすることで、AIの利点を活かしながらも、記事の「魂」は自分のものとして保つことができるのです。
この方法を実践するようになってから、AIとの付き合い方にも少しずつ自信が持てるようになってきました。完璧な解決策とは言えないかもしれませんが、一つの道筋として見えてきた気がします。
そして「同じような記事が複数存在してしまっている」という点については、後から振り返って整理整頓をすればよし。
記事そのものを削除するのではなく、まとめ記事を書いて「この記事は◯◯という新しい記事にまとめています。コチラをお読みください」などと誘導するのが得策です。
最後にひとこと
8年間、2300記事以上。ここまで書き続けてこられたのは、やはり「自分の言葉で伝えたい」という強い思いがあったからこそです。
もちろん、しょっちゅう挫けそうになることもありましたが、読者の皆様からのあたたかい反応に支えられ、ここまで至れました。
生成AIは確かに強力な味方です。しかし、あくまでも「補助ツール」として活用していく。そんなバランス感覚を持ちながら、これからも更新を心がけていきたいと思います。
この記事を読んでくださっている皆様も、同じような悩みを抱えていらっしゃるかもしれません。
「完璧を求めすぎない」「でも、自分らしさは大切に」そんな気持ちで、ぜひ一緒にブログ運営を続けていきましょう。
私が活用しているのは「Claude」という生成AIです。ChatGPTよりもさらにエモーショナルな文章を提案してくれるのがメリット。コチラの記事も合わせてお読みください。